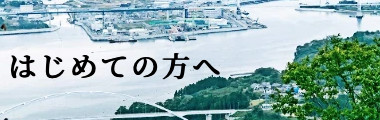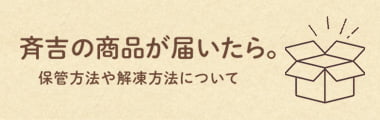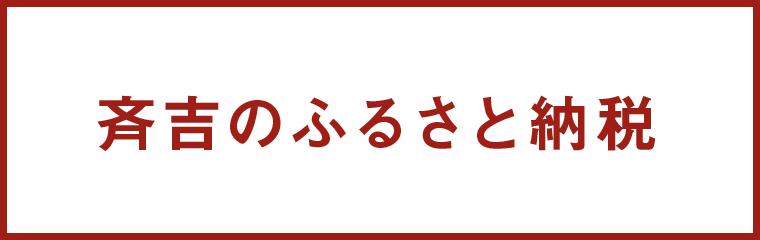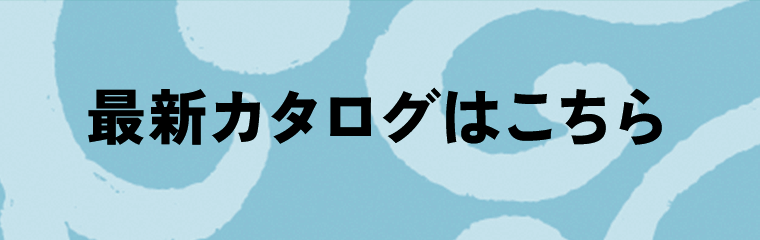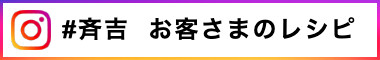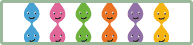2025.09.24
かつお溜め釣り漁伝来350年②
今年の4月より気仙沼の三陸新報に連載されました、「カツオがつないだ縁 和歌山県新宮市訪問同行紀①」を掲載いたします。
江戸時代に和歌山県新宮市から約1か月もかけてカツオ漁をしながら気仙沼市唐桑町鮪立にたどり着いた漁師さん達と、彼らを快く招き入れた鈴木勘右エ門さんに思いをはせながらご覧いただければと思います。

カツオがつないだ縁① 和歌山県新宮市訪問同行記
気仙沼市唐桑町鮪立にカツオ溜め釣り(一本釣り)漁が伝わり、今年で350年。先月23日~25日、市関係者が発祥地の和歌山県新宮市を訪ね、ゆかりの地を巡った。その様子を紹介する。(三浦一樹)
紀伊半島の東南部に位置し、太平洋に面する和歌山県新宮市。世界遺産である熊野三山の一つ、熊野速玉大社などが鎮座する。気仙沼からは陸路で約千キロ離れている。
江戸時代初期の1675(延宝3)年4月、紀州藩の新宮領内(現新宮市)にある三輪崎の漁師たち約70人が、5隻の漁船に乗り、カツオの群れを追って唐桑村鮪立(当時)を訪れた。生きたイワシをまき餌にした、現在のカツオ一本釣りの原型である溜め釣り漁を、唐桑の漁師たちに伝えた。生鮮カツオ水揚げ連続日本一の気仙沼港に、カツオ文化が根付く原点になった出来事だ。
悠久の歴史に触れるため、「伝来350年」を記念し、気仙沼市関係者が新宮市を訪問した。訪問団のメンバー赤川郁夫副市長と、当時、溜め釣り漁を受け入れた鮪立の古舘・鈴木家の子孫である新宮市・気仙沼市交流推進実行委員会の鈴木伸太郎会長、戸羽芳文事務局長ら6人。
一行は、3月23日午前7時に気仙沼市を出発。一ノ関駅から東北新幹線に乗り換え名古屋駅へ。名古屋駅からは特急列車で新宮市に向かい、午後4時30分ごろ新宮駅に到着した。約10時間の長旅は、気仙沼との距離を痛感させられた。
「350年前、三輪崎の漁師たちは海路で唐桑まで来たが、約1ヵ月かかったとの文献が残っている」と、郷土史を研究している戸羽さん(71)が教えてくれた。
新宮駅では、案内役の新宮市商工観光課の津越紀宏課長、新宮市議の湊川大介さんらが出迎えた。駅の外に出ると、夕方にもかからわず汗ばむほどの暑さ。「きょうは半袖でも大丈夫でした」と湊川さん。熊野灘に近いためか時折、潮の香りが漂った。
「命懸けの航海」
現在、人口約2万5千人の新宮市。和歌山県と三重県にまたがる熊野地方の中心都市として、商業が基幹産業だが、古くは捕鯨の町としても栄えた。市内には、鯨との関わりを示す史跡などが残っている。文化庁が日本遺産として認定している「鯨山見跡」もその一つだ。
かつて、鯨を発見するとのろしを上げて知らせたというこの場所からは、カツオ溜め釣り漁発祥の地・三輪崎の港を眼下に望むことができる。
350年前、鈴木さん(81)の先祖である鈴木勘右衛門は、鮪立にたどり着いた三輪崎のカツオ漁師たちを快く招き入れた。三輪崎の漁師は当時、沖縄から三陸沿岸まで漁労技術を伝えるほど、優れた技術を持っていた。勘右衛門はいち早く、従来のカツオ一本釣りに、イワシを餌に大量に漁獲する溜め釣り漁の導入を地元漁師に働き掛けた。溜め釣りによって漁獲量は飛躍的に伸びていった。
「黒潮に乗ってカツオ漁をしながら、和船で鮪立まで来た三輪崎の漁師たち。まさに命懸けの航海だったと思う。」と鈴木さん。発症の地に立ち、先人たちの功績に思いをはせた。
「カツオがつないだ縁 和歌山県新宮市訪問同行記②」を掲載いたします。(三陸新報より)
奈良時代に東北の蝦夷を征討する為に岩手県一関市の室根山に分霊された熊野信仰が、なんと江戸時代のカツオ溜め釣り漁伝来につながっているとの事です。正に「縁」を感じます。

新宮市と唐桑とのつながりを語る上で、切り離せないのが熊野信仰だ。カツオ溜め釣り漁が鮪立に伝来する、はるか950年以上前にさかのぼる。
奈良時代の718(養老2)年、多賀城の鎮守府将軍・大野東人が、東北の蝦夷征討祈願のため、元正天皇に願い出て、熊野神を室根山(岩手県一関市)に勧請(分霊)した。
熊野本宮(現在の和歌山県田辺市)からの御神霊を奉じた船団は、太平洋沿岸を北上。5ヵ月かけて唐桑村鮪立(当時)に到着し、室根山に熊野神を祭ったとされるのが、現在の室根神社である。
この時、勧請した一行の一員だったのが、鮪立の古舘・鈴木家の先祖である「鈴木左衛門慰穂積重義」だ。子孫がそのまま鮪立に住み着いたことで、後に紀州のカツオ漁師を迎え入れることにつながる。
気仙沼市の訪問団一行は2日目の24日午前、熊野神を祭る新宮市内の速玉大社を参拝した。同大社は全国に3千以上ある熊野神社の総本宮で、鮮やかな朱色の社殿がひときわ美しく、威厳があった。
神事の後、メンバーは上野顯宮司(71)から熊野信仰などについて説明を受けた。上野宮司は、全国の熊野神社の3分の2が、東日本に集中していることを指摘。熊野信仰、そして祭礼の文化が、東北の地にも色濃く残っている-と解説した。
「奉加帳」を公開
速玉大社内にある神宝館などには、室町時代の将軍足利義満らが奉納した古神宝類など千点以上の国宝が所蔵されている。さまざまな貴重な資料も展示されているが、今回、唐桑に関わりのある一冊の文書が、訪問団のために特別に公開された。
室町時代のものとされる「平家奉加帳」で、同大社への寄進の記録だ。その中に「真崎平光家」「小蘭木平義綱」と書かれている。同行した戸羽芳文さん(71)によると、当時、唐桑の小原木地区を治めていた城主2人の名前で、武運長久の神として、熊野神を崇拝していたことが分かる貴重な資料だという。
「熊野神の室根への勧請以降も、唐桑の人々が熊野を信仰していたという証だ」と戸羽さん。脈々とつながってきたことが、カツオ溜め釣り漁伝来にも大きく影響したのではないか-とみている。
熊野三山である熊野速玉大社、那智大社(那智勝浦町)、本宮大社(田辺市)のうち、速玉大社は2028年に創建1900年の節目を迎える。
「その際にはぜひ、唐桑の皆さんにも来ていただきたい」と上野宮司。末永い交流を願っていた。(三浦一樹)
「カツオがつないだ縁 和歌山県新宮市訪問同行記③」を掲載いたします。(三陸新報より)
新宮市と唐桑町の交流発展の中心となった故屋敷満雄さんはじめ、人々のつながりや行動力に感銘を受けるお話です。

新宮市中心部から、車で10分ほどの場所にある三輪崎地区。350年前、唐桑・鮪立にカツオ溜め釣り漁を伝えた漁師たちの出身地だ。海岸沿いの集落には、平屋の民家が密集し、漁村の面影を残している。
訪問団メンバーの新宮市・気仙沼市交流推進実行委員会の鈴木伸太郎会長(81)と戸羽芳文事務局長(71)が、スケジュールの合間を縫って、ある一軒家を訪ねた。新宮市議会元議長の屋敷満雄さん(故人)宅だ。
「屋敷さんが、気仙沼と新宮の交流の懸け橋になってくれた。本当に感謝しています」。屋敷さんの仏前で、鈴木さんと戸羽さんが静かに手を合わせた。
20年前に唐桑へ
気仙沼市と新宮市で、市民レベルでの交流が本格化したのは20年前の2005年。当時、和歌山の那智勝浦港に水揚げしていた唐桑町の近海マグロはえ縄船の漁労長が、カツオ溜め釣り漁の発祥地である新宮市で、唐桑に伝わる崎浜大漁唄い込みのルーツを探ろうと、地元の新聞社に情報提供を呼び掛けたのがきっかけだった。
その記事が屋敷さんの目に止まり、同年11月屋敷さんら新宮市の訪問団一行が「唐桑牡蠣まつり」に合わせて気仙沼市を初めて訪れた。屋敷さんらは、三輪崎のカツオ漁師たちを受け入れた鮪立の古舘・鈴木家も訪れ、そこで溜め釣り漁伝来の歴史をあらためて確認。以来、新宮と唐桑の関係者が何度も行き来するなど、交流を深めあってきた。
物心両面で支援
「屋敷さんは、『カツオ漁を伝えた歴史を、われわれ新宮市民が知らないのは恥ずかしいことだ』との強い思いがあった。豪快でとても明るい方だった」と、人柄を懐かしむ鈴木さんと戸羽さん。2011年3月の東日本大震災、同年9月に紀伊半島を襲った台風被害の際に、物心両面で相互支援した。
17年3月には唐桑の訪問団80人が郷土芸能「唐桑ものがたり」を新宮市で披露するなど、両市の絆はより強固なものとなり、翌年の10月気仙沼市と新宮市は「歴史・文化・産業交流都市協定」の締結に至った。
両市の交流発展に尽力した中心人物の屋敷さんは昨年、病でこの世を去った。享年78歳だった。
「こうして気仙沼の方々に新宮まで足を運んでいただき、父も天国で喜んでくれていると思う」。こう語るのは、20年前、父親と一緒に始めて唐桑を訪れた長男の博一さん(53)。戸羽さん、鈴木さんとの久しぶりの再会を喜び、ほほ笑む父の遺影を見つめた。(三浦一樹)
「カツオがつないだ縁 和歌山県新宮市訪問同行記④」を掲載いたします。(三陸新報より)
カツオ溜め釣りの発祥地である三輪崎地区。海水温上昇などの気候変動に伴いカツオ漁に関わる人々の営みも変化しているようです。現代の状況に合う形で今後も漁が続いていく事を願います。

緑や白の長い竿が付いた小型船が、10隻ほど係留されている。新宮市の三輪崎漁港。昼前、漁を終えた漁師が次々と帰港し、朝に漁獲したばかりのカツオを水揚げしていた。
三輪崎地区で行われている「ケンケン(ひき縄)漁」で漁獲したものだ。この日水揚げされたカツオは十数匹だったが、大きいサイズでは4キロのものもあり、鮮度抜群。地元漁業者によると、「漁獲後、すぐに1匹ずつ活け締めしているため」という。
視察したメンバーも「タイミング良く、新宮でカツオの水揚げが見られるとは。きれいなカツオだ」と声を弾ませた。
ケンケン漁は、船の両側などに竿を張り出し、疑似餌付きの釣り糸をたらして船を走らせながら、かかった魚を1匹ずつ釣り上げる。明治時代に広まったとされ、和歌山県内では黒潮に乗って春に沿岸を北上するカツオを狙った伝統的漁法として、三輪崎だけでなく、近隣の串本町や、すさみ町などでも盛んだ。ブランド化され、東京市場などにも出荷されている。
「ケンケン」という名前の語源は、「カツオが水面をケンケンするように飛び跳ねるため」「疑似餌が海面を跳ねる様子を指している」など、諸説ある。
イワシを餌にしたかつお溜め釣り(一本釣り)の発祥地である三輪崎では、25年ほど前まで地元の一本釣り船によるカツオ漁が行われていたが、今は姿を消した。
「カツオの餌となるカタクチイワシが近場の定置網で取れなくなったのと、後継者不足でやめざるを得なかった」。三輪崎漁業協同組合の海野義尊組合長(75)が理由を語る。
海野組合長は、三輪崎最後のカツオ一本釣り船「益栄丸」(17トン)の漁労長を務めた。中学卒業と同時に兄の船に乗り、毎年、九州~千葉・勝浦にかけてカツオの群れを追った。55歳で下船後は、ケンケン漁やアワビ漁、伊勢エビ漁などで生計を立てた。
「カツオの溜め釣り漁を唐桑など全国に伝えた町として、一本釣り船がなくなってしまったのは寂しい」と海野組合長。三輪崎では現在、12軒がケンケン漁を行っており、「一人で操業でき、すぐ近場で漁ができる。コストがそれほどかからないのが、最大の魅力だ」という。
海洋環境変化で年中水揚げ
海野組合長によると、海水温上昇など近年の海洋環境の変化は紀伊半島沿岸でも顕著になっている。これまでケンケン漁のカツオは主に春に漁獲、水揚げされていたが、「今は年中釣れるようになった。正月でもカツオが揚がる」と話す。
漁法は異なれど、三輪崎では今も「カツオの灯」は消えていなかった。海の恵みに感謝し、1匹1匹を大切に扱おうとする精神が、漁師たちに根付いている。(三浦一樹)

 創業大正10年。気仙沼から「美味しい食卓 豊かな暮らし」をお届けします。
創業大正10年。気仙沼から「美味しい食卓 豊かな暮らし」をお届けします。